「子どもの願い」と「教師の願い」の接点を単元のゴールに設定する〜第5学年保健・健康教育「けが攻略シート作り」〜
公開日: 2025年10月8日水曜日
本校の5年生にとって一大行事である臨海学校。
遠泳をはじめとする野外プログラムに向け、子どもたちは強い思いを抱いています。
本校養護教諭・村上教諭はその実態を踏まえ、臨海学校のしおりに自分たちが作成した「けが攻略シート」を掲載することを単元のゴールに据えました。これにより、子どもたちは「みんなが安心して臨海学校に臨めるようにしよう」という共通の目的意識をもって取り組むことができました。
まず素晴らしかったのは、見る限り、すべての子どもたちが話題に沿って話したり、友達の話を聞いて反応したりすることができていたことです。これは、この単元で行う活動「けが攻略シートづくり」が子どもたちにとって意味あるものだと感じられるものであったことが背景にあったのではないかと思います。
みんなで同じ話題で対等に議論する姿からは、このクラスのまとまりを感じますし、お互いの発言が同等に受け取られ、まさに対話を通して学んでいる姿であったと思います。
しかし、ロールプレイのところで、気がそれる子どもが出てきました。「劇」自体をエンタメとして楽しんでしまって、学習内容が置いてけぼりになっているように感じられました。ロールプレイ自体がこの教材に合わないのか、ロールプレイへの手立てが足りなかったのか定かではありませんが、いずれにせよそれまでの学習内容が高まっていくということは起きなかったように見えました。
その一方で、あえて「劇」を選ばないという子どもがいました。学級担任の安倍先生がロールプレイをしてもいいですよと全体に促した後のグループ活動で、多くのグループで劇の役割を話していいましたが、「ちょっとまって、11時までつくりかえさせて」と発言しました。
理由は、どんな場所なのか、海水温はどうなのかを知らないとどうすればいいのか本当によいことが見つからないからと話していました。すると、同じグループでエンタメとしての劇をしそうになっていた子どもも、自分のカードを見直していました。自分たちの学習を、自分たちの目的に照らして、調整するということができていたと思います。その後、海水温を調べたり、海水浴場の写真を見直したりする姿がありました。そして、やっぱり役割演技は今回の学習に馴染まないと結論づけて、原稿に何を掲載するかについてたのしそうに話し合っていきました。
重要な学びの自己調整が、集団で学んでいたからこそ行えた瞬間だったと思いました。
村上先生・安倍先生の実践から発見した、集団の学びについての気づきをまとめると、
・子どもたちが本気になる学習対象の選定がやっぱり大事。
・集団だからこそ、易きに流れることもあるし、踏みとどまれることもある。
・傾聴し合える関係性が必要。その上で、自分たちの学習の目的が揃っていれば、「意味を見いだせる事柄」に収束していく。
また、TTでの授業実践において、見取りを共有する機会をもつことで連携を促進し、子どもたちの学びの様子に基づいた授業展開ができるということも気付きでした。
まだまだ、今年度の校内研究授業は続いていきます。
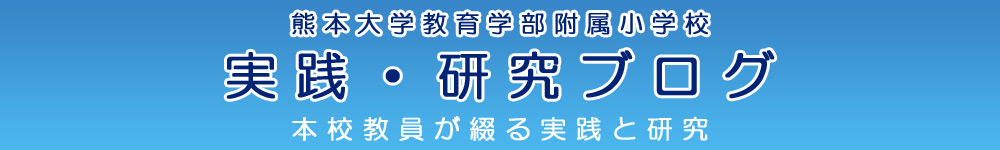


0 件のコメント :
コメントを投稿