みんなで同じ土台に立つから友達の意見を聞きたくなる〜第4学年体育科スフェリカルシュートゲーム(ゴール型ゲーム)〜
公開日: 2025年10月15日水曜日
今回ご紹介する実践は、冨永悠真教諭の体育科の実践です。
冨永教諭は、今年本校に赴任したばかりの先生です。これまでも体育科の研究会に所属してたくさんの実践研究を積んでこられました。今年は研究部に所属し、他の職員の実践に対して積極的に意見を述べたり、研究業務に関する事務をしっかり遂行してくれています。「スフェリカルシュートゲーム」についての詳細は、別の記事を参照していただきたいと思います。
https://taiiku-kumadaifuzokusho.blogspot.com/2025/07/blog-post.html
ここでは、授業を参観していて、私は、本時の授業中の子どもの様子とそれを引き出した冨永先生の働きかけについて思ったことについて述べていきます。
一番印象的だったのは、子どもの目線です。目線が一つのものに揃い、それが持続することが長いと感じました。この意味はすごく大きいと思います。授業の各展開で友達の示す動きのモデルをしっかり見たり、意見を言う友達や作戦板を見たりする子どもの姿があり、「学びにおける友達の存在の大切さ」を子どもたち一人一人が自覚しているように感じました。
その背景には様々なきっかけがあると思います。教材の魅力、普段の友達との関係性などいろいろ予想できますが、中でも事実として見えたのは、冨永先生の立ち位置の工夫です。以下の写真は、一人の子どもが黒板を使って発表した後の様子です。冨永先生は子どもと黒板の間には立たず、黒板の横で、子どもの中に入って子どもと同じ目線から話していました。どうしても子どもは先生の方を見ますが、指をさして目線を発表した子どもの残したメモに目線を移させます。先ほど、子どもたちの目線が揃う背景について述べましたが、このような一つ一つの先生の態度によって、教材の魅力、友達の意見を傾聴する態度への気づきが自然と促されていると感じました。
多様性を大切にすることが新しい指導要領に盛り込まれそうですが、多様なまま個別化孤立化していくという意味では決してないと思います。同じ土台に立ち、同じものを見てみる中で、意見の多様さやよさに気づいたりそれらを基に自分の考えを更新したりすることによって、多様な個が尊重される集団が形成されていくと思います。
民主的な社会が到来するよう、これからの教育について職員みんなで考えながら、授業実践を重ねていきたいと思います。
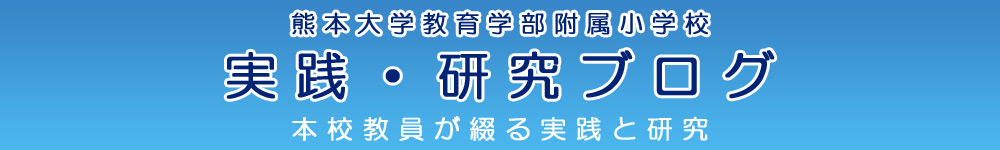




0 件のコメント :
コメントを投稿