ついに実現!県小国研・市算研とのコラボレーション〜令和7年度夏の実践研修会について〜
公開日: 2025年10月10日金曜日
今年も夏の実践研修会を行いました。
今年の夏の研修会は、熊本の教育研究を牽引する2つの団体
熊本県小学校教育研究会国語部会(以下、県小国研)様と
熊本市算数教育研究会(以下、市算研)様の
協力を得て、同じ単元・同じ時間の授業を
附属小職員と提案し合うという
コラボ企画を実施いたしました。
算数の授業者は、市算研からは山口翔乃介教諭、本校からは内田武瑠教諭
の4名でした。
国語の授業は、3年「カミツキガメはわるものか」(東京書籍)の単元開きを提案し合いました。
県小国研の中里教諭は、「言葉の力」を明確にすることから始められました。
この単元でどんな言葉の力がつくとよいか、子ども自身が見通しをもった上で教材文を読んだり話し合ったりしていくことを大事にされていました。そして、本文を大切にされている姿勢から、国語の授業が大切にすべき言葉の見方・考え方について改めて考えさせられました。
一方、本校の木下教諭は、「動作化」をふんだんに取り入れた授業を提案しました。
さまざまな立場の人から見た「カミツキガメ」の姿を捉えることで、題名にもなっている「悪者か」という筆者の問いかけについて考える授業でした。
さまざまな立場の人から見た「カミツキガメ」の姿を捉えることで、題名にもなっている「悪者か」という筆者の問いかけについて考える授業でした。
市算研の山口翔之介教諭は、「同じものを買うのに値段が違う」という問題場面を提示し、子どもたちがその理由を探りながら解き明かしていく授業を提案してくださいました。とてもよく練られた問題で、+bの意味を見つけ出した子どもたちは、ほくほくとした表情で算数の楽しさを味わっているようでした。
内田武瑠教諭は、「だいたい比例する」という関係を見いだすことをねらいとして、教材の選定にこだわって授業に臨みました。子どもたちが自分の予想を確かめながら学びを進められるよう、問題設定や学習環境が工夫されており、重さを測って考えを更新していく姿が随所で見られました。
4人の先生方は、それぞれの授業の中で、ご自身が大切にしていることをしっかりと示してくださいました。
今回のコラボ企画が目指していたのは、まさにそのような授業の中で「本当に大切なことは何か」を見つけ出すことでした。そこには、きっとさまざまな答えがあるはずです。参加者の皆さんにとって、ご自身の考えをもったり、より明確にしたりする機会になっていれば幸いです
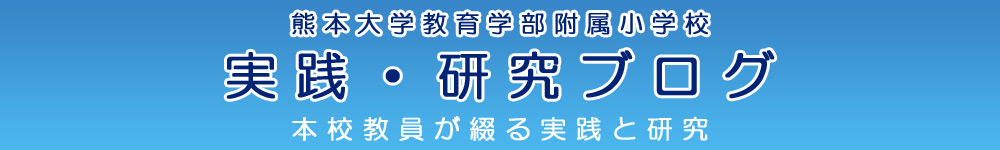






0 件のコメント :
コメントを投稿